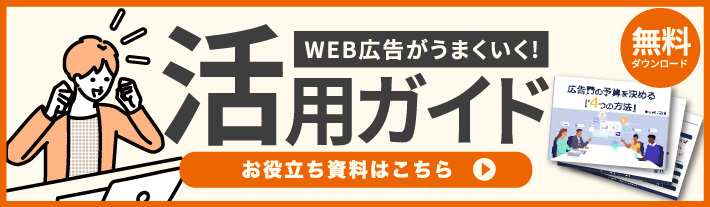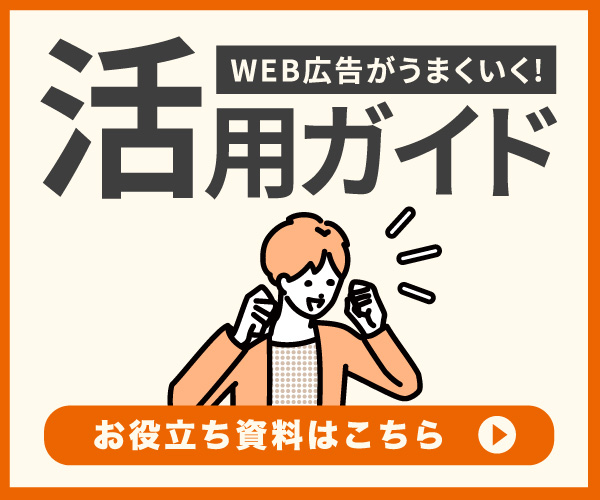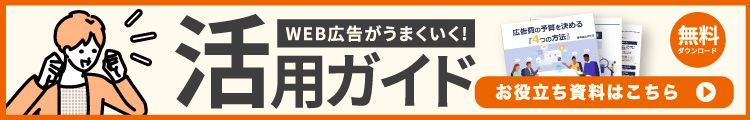企業のYouTubeチャンネルを開設したのに、 全く視聴者に見られないという方は多いでしょう。 &n…
Read more【絶対NG】企業YouTube運用の落とし穴「ブランドを壊す」ダメ施策6選

目次
YouTubeチャンネルは企業にとって顧客やユーザーとの接点を広げ、
認知力・ブランド力を強化するための絶好のツールです。
しかし、安易な運用や小手先のテクニックに依存するとかえってブランドイメージを損ない、
視聴者からの信頼を失う致命的なリスクがあります。
この記事では、企業YouTubeアカウントが絶対に避けるべき失敗や「やってはいけないこと」を、具体例を交えながら解説します。
Youtube運用ダメ施策①再生回数稼ぎの「クリックベイト」は逆効果

一見、派手なサムネイルや過激なタイトルで注目を集める「クリックベイト」と呼ばれる手法は有効的な手段に思えます。
実際にそれを推奨するYouTubeコンサルの業者もいるほどです。
しかし、サムネイルやタイトルにつられて動画を視聴したユーザーが
その動画の内容に落胆してすぐに離脱してしまえば、結果的に再生時間が短くなり、YouTubeのアルゴリズムに悪影響を及ぼします。
現在、「ユーザーの視聴維持率」はYouTube上でも非常に重要な指標です。
そうして失った信頼を回復するのは至難の業です。
例えば「○○を使えば売上100倍に!」とタイトルで煽ったものの、肝心の内容は曖昧な解説だけという動画があったとします。
過激なタイトルと実際の内容の乖離が見られると、ユーザーからの低評価にもつながりますし、離脱率・視聴維持率の低下にもつながります。
再生数を短期的に稼ぐよりも、信頼される情報を地道に提供し、継続的なファンを増やす運用が重要です。
Youtube運用ダメ施策②他社や競合を批判する動画は厳禁

競合との違いをアピールするために、「○○社のサービスは時代遅れ」と露骨に批判し、競合と自社製品の比較動画で、他社の欠点ばかり強調したとします。
このように他社製品やサービスを批判するヘイト動画は、短期的には注目を集め、再生数を稼げるかもしれません。
しかし、視聴者から「品がない」「信頼できない」と受け取られるリスクが高く、企業イメージを損なう可能性が非常に高いです。
YouTubeチャンネルを伸ばすためには競合を批判するのではなく、自社の強みを強調したコンテンツ作りに注力し、ポジティブな印象を与える必要があります。
Youtube運用ダメ施策③アルゴリズムを過信した投稿頻度の乱発

アルゴリズムを意識して、「とにかく本数を増やせば伸びる」という誤解に陥る企業は少なくありません。
確かに投稿頻度はYouTube上でも重要な要素にはなります。
しかし、質の低い動画を連発すると視聴者が離れ、チャンネル全体のエンゲージメントも低下します。
実際にとある企業では、毎日投稿にこだわった結果、雑な編集や内容が薄い動画を多発することになってしまい、
無理に動画数を増やしたため、企業価値が伝わらず逆効果になったケースもあります。
視聴者にとって価値のあるコンテンツを優先し、無理のないペースで投稿することが重要です。
質さえよければ、1,2週間に1本の投稿頻度でもしっかりと伸ばすことができます。
Youtube運用ダメ施策④広告色が強すぎるコンテンツは避けるべき

YouTubeは広告的なコンテンツに極めて敏感なプラットフォームです。
視聴者は「押し売り感」を嫌い、広告色が強すぎる動画には興味を示しません。
特に企業アカウントでは、広告要素を抑えた価値提供型のコンテンツが求められています。
例えば、3分間の動画のほとんどが自社製品の宣伝で、視聴者に役立つ情報が少なく、CMと変わらない内容の動画を投稿したとします。
広告運用で成り立っているYouTubeの運営側が、そのような動画を評価すると思いますか?
また、ユーザーもそのような動画を求めていると思いますか?
まずは視聴者にとって有益な情報が何であるかにしっかりと焦点を据えなければなりません。
自分たちの発信したいことばかりを投稿しても視聴回数は中々伸びません。
まずはユーザー目線のコンテンツを中心に構成し、その中でさりげなく自社製品を紹介する「コンテンツマーケティング型」のアプローチを心がけましょう。
Youtube運用ダメ施策⑤コメント欄や視聴者の声を無視する

YouTubeは「双方向コミュニケーション」が重要です。
コメント欄を放置したり、批判コメントを削除するような対応をすると、企業の誠実さを疑われる原因になります。
ユーザーのフィードバックを無視せずにしっかりとコミュニケーションをとることで、リピーターの固定化、信頼関係の構築を狙うことができます。
ある企業様から以下のようなご質問をもらったことがあります。

これに対して私の回答は、「動画内容に関係のあるアンチコメントは絶対に消してはダメ」というものです。
例えば「ダイエットジム」の企業がダイエット方法について紹介する動画を投稿したところ
「今の○○政権は・・・」といった関連性のない謎のアンチコメントがついた場合は、何のシナジーも生まないので消しても良いです。
しかし、「そんなダイエット方法ダメじゃない?」というようなアンチコメントであれば、真摯に対応し、コメントに返信していきましょう。
その誠実な対応に、他の優良なユーザーは惹かれるかもしれません。
このアンチコメント自体にも反応する別のユーザーも出てきますし、そのようにコメント欄が盛り上がると、一度訪れた人がまた訪れて・・・という循環も生みます。
企業の信頼度を高め、ファンとの関係を深めるためにもコメントへの返信はしっかりと行っていきましょう。
Youtube運用ダメ施策⑥トレンドに乗るだけの中身のない動画

トレンドを追いかけるだけで内容が伴わない動画は、瞬間的な注目を集めても長期的にはブランドの信頼性を損ねます。
「とりあえず流行っているから」と安易に投稿すると、視聴者は次第に興味を失い、再生数が伸びなくなります。
実際の企業様でも、SNSで話題のネタを拾って流用したが、自社と関連性がなく中途半端な印象の動画を投稿したという事がありました。
その動画単体では少しアクセスが増えたのですが、以降に続く動画はそれ自体止まった関係がなかったため全く伸びなかったという事例があります。
トレンドだけに頼った動画で一時的に再生数は増えてもその後視聴者が離脱します。やはり重要なのは視聴者をいかに維持できる動画であるかです。
自社のコンセプトに合うトレンドだけを取り入れ、ブランドに一貫性のある内容で視聴者を惹きつけましょう。
Youtube運用ダメ施策:まとめ
この記事では、YouTube運用において企業が避けるべき「やってはいけないこと」を具体的に紹介しましたが、重要なのは、企業の理念やブランドを大切にする姿勢です。
YouTube運用で重要なのは「誠実さ」と「一貫性」です。
小手先のテクニックに頼らず、価値あるコンテンツを一貫して発信することで、長期的な成長が目指せます。
また、双方向のコミュニケーションを意識し、視聴者との関係を深めることで、企業の信用性も固めていけます。
視聴者から信頼される運用を目指し、YouTubeチャンネルを躍進させていきましょう!
資料ダウンロードはこちら

1,000本以上の広告を運用してきた代理店が教える『WEB広告運用3つの超基本』
フォームに必要事項をご記入いただくと、無料で資料ダウンロードが可能です。